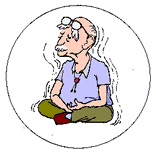秋晴れのさわやかな午後のひとときである。
腰と膝が痛いという、翁先生よりも十才程若い御婦人で、今日で三回目の患者さんが来た。
「こんにちは、どんな具合ですか?」と私はいつものようにたずねながらも形態観察をしている。
「家で試してみました?」とこれで三回目の質問なのだ。
「なかなかむずかしくてェ」とニコニコしながら言い「お願いしますぅ」とベットに仰向けに寝た。
みんななかなか自分でやってみようなんて思ってくれないものだなぁ、と私はチョコチョコ触診を始めた。
顔を視ながら腰の両側を抱き込むようにさぐっていると、突然顔をヒンマゲて「ヒィーッ!」と息を吸ったと思ったら「ヘークションー」とおもいっきりクシャミが出た。
ところが、そのクシャミが一回だけだったのに、なぜか二つの音が同時に鳴ったのだ。
ひとつの音はもちろんハクションで、もうひとつの音はどういうわけかオシリのあたりから発生し、なにやら聞き覚えのあるニブイ音で「ブッー」という低音であった。
私といなだセンセは、それをすぐに聞き分けたし、彼女だってしっかり気づいたにちがいない。
つまり彼女は無意識のうちにクシャミと『へ』を一緒にやってしまったのだ。
しかし、そのときは運よく受付のミヨチャンだけには知られずに事無きを得た。
私は無意識に彼女のオシリのあたりから遠ざかるように身を引き、少し間をおいてから、いなだセンセに膝裏の圧診をお願いした。
センセも彼女から離れた位置で大きく深呼吸をしてから神妙に触診を始め、彼女も少し戸惑いの表情をして、無言でシドロモドロしていた。
私は「オナラしましたぁ?」などとも言えなくて、わざと知らないふりして「風邪ぎみですかぁ?」とクシャミしか聞こえなかったように問いかけたのだ。
すると彼女は「エェ、チョットネ」と<カゼ>でも<へ>でも通じるシャレた返事をして、ハニカミながらホホエンダ。
私は、なんと正直な人だろう…と思いつつ彼女の言葉に感動していた。
いなだセンセも少し鼻声になりながらも、あれこれ繰法にいそしんでいる。
私は腕を組み、彼女の頭の方に立ってみていたのだが、どうしてかそのことをミヨチャンに知ってほしくなり、「このオバチャン、さっきのクシャミと同時に『へ』したんだゾ」。
と紙切れに書いて見せたのだ。
さぁここからが大変だ。
ミヨチャンは静まりかえった雰囲気の中でクスクスと首を縮めて笑い出し、しだいに本気に涙をこぼしてヒクヒクと苦しみ出してしまったのだ。
そんな姿を見ていたら私まで可笑しくなってしまい、どこかへ逃げるしかなくなり、吹き出しそうな笑いをこらえてゆっくりと急いでトナリの部屋へかけこんだ。
追いかけるようにミヨチャンもお腹をかかえて入って来て、しゃがみこんで泣いた。
いやはやこんな体験は初めてであった。
いなだセンセは私達がどうしてトナリの部屋へ行ったのかわからなかったらしく、不思議に思いつつもひとり懸命に指導にあたっていた。
30秒程して私は平然と戻って来たが、ミヨチャンはなかなか自分の席に帰れなかった。
ミヨチャンは減給ものである。
しばらくして私も真面目に指導に加わりはしたが、私の耳は妙な音色をちらりほらりと思い浮かべ顔は時々ニヤッとし、鼻は不安の色を隠せなかった。
そしてあれこれと指導するうちに、何故か私は彼女の足の平をくすぐってみたくなり、「ちょっとくすぐってみますよォ」と真剣にくすぐり始めた。
「どっちの足がくすぐったい?右。左?」とほとんど遠慮なく堂々とやる。
彼女はキクキクと足腰を動かしながらも、「左の方がくすぐったいですぅ」と子供にでも返ったようにエヘヘ、オホホと笑いながら答えてくれた。
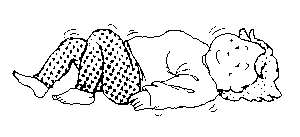
20秒ぐらいつづけてくすぐり、一休みし、又くすぐる。
「どんどん動いていいですよォ」などといいながらも、あまりお腹に力が入らねばいいなぁ、と少し心配しながらコチョコチョやった。
そんなこんなで立って歩いてもらったら、上機嫌な顔で「なんかスゥーッとして楽になりました。」とスタスタ歩いている。
私もなにが効いたかわからないけど「無意識の行為は全部バランスをとるように出来ているんですよ」といって指導が終わった。
近くで菊の花が笑っていた。
――「温古堂ものがたり」 完――
|